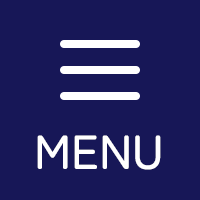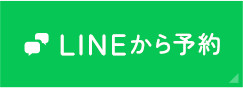甲状腺機能亢進症
甲状腺機能亢進症(こうじょうせんきのうこうしんしょう)は、喉仏のすぐ下にある、蝶の形をした「甲状腺」という臓器が必要以上に働き、甲状腺ホルモンを過剰に分泌してしまう病気です。
甲状腺ホルモンは体の新陳代謝(エネルギーの利用や生成)を活発にする役割があります。ホルモンが多すぎると、体は常に全力疾走しているような状態になり、心身にさまざまな症状があらわれます。
甲状腺機能亢進症の原因
甲状腺機能亢進症を引き起こす原因はいくつかありますが、最も代表的なものはバセドウ病です。
バセドウ病
本来、体を守るべき免疫に異常が生じ、自分の甲状腺を刺激する特殊な抗体(TRAb:ティーアールエービー)が作られてしまう自己免疫疾患です。この抗体が甲状腺を絶えず刺激するため、ホルモンが過剰に作られ続けます。20~40代の女性に多く見られますが、男性や他の年代でも発症します。
その他の原因
甲状腺にできた腫瘍(しこり)が自律的にホルモンを過剰に産生するプランマー病や、甲状腺に炎症が起こることで蓄えられていた甲状腺ホルモンが一時的に血液中に漏れ出す無痛性甲状腺炎や亜急性甲状腺炎などがあります。
甲状腺機能亢進症の症状・自覚症状
全身の代謝が異常に高まることで、次のような症状が出ます。複数の症状が当てはまる場合は注意が必要です。
全身の症状
- 動悸、息切れ、頻脈
- 多汗、暑がり
- 食欲旺盛なのに体重減少
- 疲労感、倦怠感
- 手指の震え
- 軟便、下痢
- 筋力低下
- 月経不順
精神・神経の症状
- イライラ、怒りっぽい
- 落ち着きがない
- 集中力の低下
- 不眠
バセドウ病に特徴的な症状
- 甲状腺腫(首の腫れ)
- 眼球突出(目が前に出る)
- 物が二重に見える
- まぶたの腫れ
※「甲状腺腫」「眼球突出」「頻脈」は、バセドウ病の代表的な3症状で「メルゼブルクの三徴」と呼ばれますが、全てがそろうとは限りません。
甲状腺機能亢進症が疑われる時に行う検査
問診
自覚症状、既往歴、家族歴、体重の変化などについて詳しくお伺いします。
血液検査
甲状腺ホルモン(FT3, FT4)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)、バセドウ病の原因となる自己抗体(TRAb, TSAb)の値を調べます。亢進症ではFT3・FT4が高値、TSHが著しく低値となります。
甲状腺超音波(エコー)検査
甲状腺の大きさや腫れの様子、血流の状態、しこりの有無などを画像で確認します。バセドウ病では、甲状腺内の血流が非常に増加している様子(火炎状血流:thyroid inferno)が特徴的です。
その他の検査
動悸や不整脈の症状がある場合には心電図検査を、必要に応じて放射性ヨウ素を用いた甲状腺摂取率シンチグラフィなどを行うこともあります。
甲状腺機能亢進症の治療方法
治療法には大きく分けて3つの選択肢があり、患者さんの年齢、症状の重さ、ライフスタイルなどを考慮して、専門医と相談しながら最適な方法を選択します。
薬物療法(抗甲状腺薬)
甲状腺ホルモンの合成を抑える薬(メルカゾール®、チウラジール®/プロパジール®など)を内服します。多くの患者さんで最初に選択される治療法で、外来で手軽に始められます。定期的な通院と血液検査で薬の量を調整しながら、甲状腺機能を正常に保ちます。
アイソトープ(放射性ヨウ素)治療
放射性ヨウ素が入ったカプセルを飲む治療法です。放射性ヨウ素が甲状腺に取り込まれ、甲状腺の細胞を内側から破壊してホルモンの産生を減らします。効果は高いですが、将来的に甲状腺機能低下症になる可能性があります。妊娠中・授乳中の方や若年者には行えません。
手術療法
ホルモンを過剰に産生している甲状腺組織そのものを外科的に切除する方法です。比較的早く効果が得られますが、入院が必要となり、首に傷が残ります。薬の副作用が強い場合や、甲状腺腫が非常に大きい場合などに選択されます。
甲状腺機能低下症
甲状腺機能低下症(こうじょうせんきのうていかしょう)は、喉仏の下にある「甲状腺」の働きが悪くなることで、生命活動に不可欠な甲状腺ホルモンの分泌が不足してしまう病気です。
甲状腺ホルモンは、体の新陳代謝を促進する役割があるため、このホルモンが足りなくなると、体全体の活動が鈍くなり、心身に様々な不調が現れます。体が「冬眠モード」に入ったような状態になり、甲状腺機能「亢進症」とは、全く逆の状態になる病気です。
甲状腺機能低下症の原因
 甲状腺機能低下症の最も一般的な原因は橋本病(慢性甲状腺炎)です。
甲状腺機能低下症の最も一般的な原因は橋本病(慢性甲状腺炎)です。
橋本病(慢性甲状腺炎)
バセドウ病と同じく、免疫システムの異常によって起こる自己免疫疾患です。自分の甲状腺組織を異物とみなして攻撃する抗体(抗TPO抗体、抗Tg抗体)が作られ、甲状腺に慢性的な炎症が起こります。その結果、甲状腺の細胞が徐々に破壊され、ホルモンを十分に作れなくなってしまいます。成人女性に多く見られます。
その他の原因
甲状腺がんやバセドウ病の治療のために、甲状腺を切除したり、アイソトープ(放射性ヨウ素)治療を受けたりした後に、機能低下症になることがあります。また、生まれつき甲状腺がない、またはホルモンをうまく作れない先天性甲状腺機能低下症や、薬剤の副作用として起こることもあります。
甲状腺機能低下症の症状・自覚症状
甲状腺ホルモンが不足すると、全身の代謝が低下し、症状はゆっくりと現れるため、年のせいや疲れ、更年期障害、うつ病などと間違われることも少なくありません。
全身の症状
- 常に疲れている、無気力、だるい
- 食事量は変わらないのに体重が増える
- 寒がりになる
- 体のむくみ(特に顔や手足)
- 声がかすれる、しゃがれる
- 脈がゆっくりになる(徐脈)
- 便秘
精神・神経・皮膚・毛髪の症状
- 物忘れ、集中力の低下
- 眠気、ぼーっとする
- 抑うつ気分
- 皮膚が乾燥し、カサカサになる
- 髪や眉毛(特に外側)が抜ける
※重症化すると意識障害(粘液水腫性昏睡)に陥ることもありますが、非常にまれです。
甲状腺機能低下症が疑われる時に
行う検査
血液検査
甲状腺ホルモン(FT4, FT3)と甲状腺刺激ホルモン(TSH)の値を測定します。低下症では、FT4が低値、脳が「もっとホルモンを出しなさい」と命令を出すためTSHが高値になるのが特徴です。また、橋本病の原因となる自己抗体(抗TPO抗体, 抗Tg抗体)の有無も調べます。
甲状腺超音波(エコー)検査
甲状腺の大きさや内部の状態を確認します。橋本病では、甲状腺が腫れていたり、内部が不均一に見えたりすることがあります。
甲状腺機能低下症の治療方法
甲状腺機能低下症の治療は、不足している甲状腺ホルモンを薬で補う「甲状腺ホルモン補充療法」が基本です。
薬物療法
合成甲状腺ホルモン製剤(レボチロキシンナトリウム、商品名:チラーヂンS®など)を毎日服用します。この薬は、もともと体内で作られるホルモンと同じ成分なので、適切な量を服用している限り、副作用の心配はほとんどありません。
少量の服用から開始し、定期的に血液検査を行いながら、その人に合った最適な量に調整していきます。多くの場合、一度治療を開始すると生涯にわたって服用を続ける必要がありますが、きちんとコントロールされていれば、健康な人と全く変わらない生活を送ることができます。自己判断で薬をやめたり、量を変更したりしないことが非常に重要です。
日常生活での注意点
橋本病の方でも、甲状腺機能が正常であれば特に食事制限はありません。しかし、甲状腺機能が低下している場合、ヨウ素(昆布、ひじき、わかめなどの海藻類に多く含まれる)を過剰に摂取すると、甲状腺の働きがさらに抑制されてしまうことがあります。サプリメントやうがい薬などで、ヨウ素を大量に摂りすぎないように注意しましょう。
なんとなく続く体調不良が実は甲状腺機能低下症のサインかもしれません。気になる症状があれば、お近くの内科、または内分泌内科を受診してください。